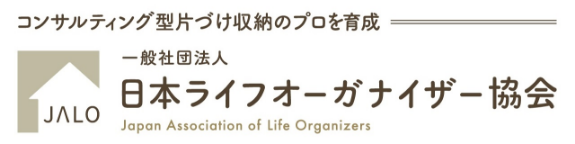先日の勉強会でのこと。
障害者差別解消法にある
『合理的配慮の提供』という言葉を、初めて聞きました。
(社会福祉士の資格はもはや化石)
ライフオーガナイザー🄬の勉強会ではいつもさび付いた脳に刺激を与えてもらっています。
きっと、読んでくださっている方の多くは私と同様、『???』と思われたはず。
なんかムズカシソウ、と去ってしまわないで!
だってね、ハンデをもって生きづらいと
感じている方のこと、
私たちはもっと知ってもいいと思うんですよ。
この法律は、障害のある人もない人も、
互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
今回いただいた資料から一部引用しながら私の学びをまとめてみました。
障害者差別解消法は思いやりが根っこ
障害者差別解消法
(※正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は
平成28年4月1日から施行されています。
当初は
行政や公共団体等が「合理的配慮の法的義務あり」
民間事業者(個人事業主含む)は「合理的配慮は努力義務」ということでしたが
昨年令和3年(2021年)に法律が改正され、
民間事業者(個人事業主含む)も「合理的配慮の法的義務あり」に変わりました。
不当な差別的取扱いの禁止って?
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。
差別が禁止と書かれていますが、
私たちの日常生活や仕事の現場で
気づかずにやってしまっている事がないかと今も考えています。
以前、ある車椅子生活をされている人が
世の中の大半の建物は
自分にとって障壁になっているとblogで書かれていました。
施設やお店を利用しようにもエレベーターがない。
通路が狭くて入れないから
誘われても遊びに行くことができない。
誘ってくれる友達に
悪気がないのはわかっているけど、不快な気持になる、と。
これも差別の種類にはいるかもしれません。
想像力が足りないせいでハンデのある方を
排除してしまっていないか、
そんな視点を忘れたくないと思いました。
合理的配慮の提供を考えてみた
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。
そういえば、私の自宅は全然バリアフリーではありません。
もしも自宅レッスンに来ていただくことになれば「合理的配慮」を行う必要があります。
この場合は自宅以外に場所の変更する、
移動を個別にサポートするといったことでしょうか。
障がいは目に見えることだけではなく、
聴覚障がいや発達障がいも一見わかりません。
ヒアリングをしたり、現場で片づけ作業をする時には特に「合理的配慮」をする心構えが必要ですね。
他の人は出来るのに自分には課題になる。
人一倍努力しないといけないけれど、
それでやっと当たり前といわれる。
それでも、周囲に「助けてください」と
協力を求めないといけない状況があった時に
言い出すのに
とても勇気が必要なんだと想像します。
障がいを抱える方やその家族には
私たちが気づかない荷物を抱えておられるように思います。
そんな荷物を少しでも軽くするために
出来た法律が障害者差別解消法であり、
その具体的な方法が合理的配慮の提供だということですね。
正解が一つではないことなので、
これからも一つ一つ
丁寧に取り組んでいきたいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
●片づけコンサル
●片づけレッスン
●オーガナイズサポート
●お家づくり密着サポート
などなど、お受けしています!
お問い合わせはこちらまで